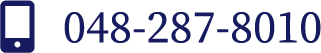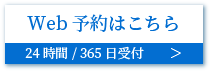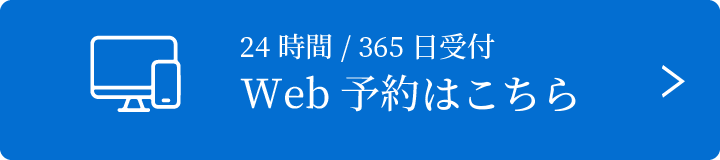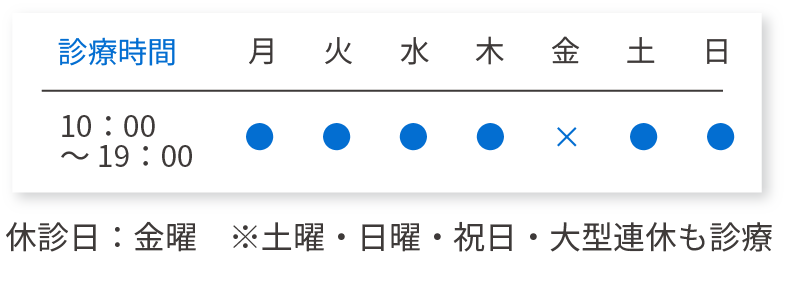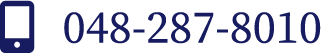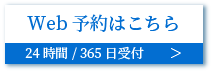親知らずの抜歯

親知らずとは、18歳以降に生えてくる歯のことで、第三大臼歯と言います。
親知らずが歯肉の中に潜っている、歯肉から一部分だけ見えているなど、真っ直ぐに歯が生えてこないことも多いです。
ですので、一番奥に生えていることから、歯ブラシが届かずに歯がよく磨けないことから、細菌感染を起こして痛みが出ることや、歯肉が腫れるなどの弊害が生じます。
当院では、痛みや腫れが極力起こらないように、安心して親知らずの治療を受けていただける設備と機材を揃えております。
親知らずでお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
こんな場合は親知らずの抜歯が必要かも…

このような症状があれば治療が必要な危険性があります。

● 親知らずが何度も腫れを繰り返す
● 親知らずが気になり始めてから、噛み合わせがズレている気がする
● 奥歯の歯肉が広範囲で腫れる
● 歯を磨いても口臭が気になる
● 親知らずが痛いのか、手前の奥歯が痛いのか分からない
● 体が疲れると親知らず周辺の歯肉が疼く
親知らずは抜く必要があるの?
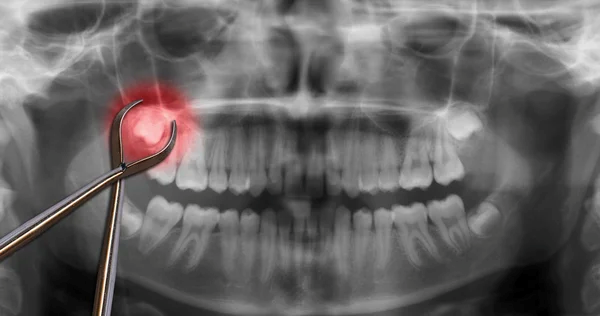
親知らず自体が生えていない、顎の骨の中に存在しているけれど感染するリスクが低い場合には、親知らずを抜歯する必要はありません。
ですが、このような場合には親知らずを抜く必要性があります。
・ 少し生えているが、歯ブラシが届かず磨けない。
・ 一度ではなく、何度か腫れたり痛みが出たことがある。
・ 親知らずの手前の歯が虫歯になりそうな角度で、親知らずが生えている
・ 親知らずが原因で口臭が出ている
上記のような弊害が生じている場合には、親知らずを抜く必要性があります。
放置しておいても経過が良くなることは、残念ながらありません。悪化を辿る一方です。
周囲の歯や、歯肉などの組織に影響を与える前に、親知らずは抜歯をお勧めすることが多いです。
当院の抜歯治療の特徴
安心して親知らずを抜歯することが出来ます

親知らずを抜歯する時に、不安になることはとても多いと思います。ですが、ご安心ください。当院では、レントゲンだけではなく、歯科用CTの設備も整えていますので、難しい生え方の親知らずでも精密な画像診断をすることで、親知らずの抜歯におけるさまざまなリスクを排除することが可能です。
予め画像診断をすることで、親知らずの付近を走行している太い神経や、血管などを傷つけることなく、安心安全な抜歯を行うことが可能です。
痛みや腫れを極力抑えた治療が可能です

親知らずの抜歯では、痛みや腫れをイメージする方も多いと思います。ですがご安心ください。親知らずの抜歯などの外科的な治療は的確な処置とスピードが肝心です。当院の歯科医師は親知らずの抜歯の症例件数が豊富ですので安心して抜歯を受けていただくことが可能です。
親知らずの抜歯治療の流れ

1.検査

レントゲンでの画像診断と、お口の中の精密検査を行います。
親知らずの状態によっては、歯科用CTでの撮影を行います。

2.治療計画の説明

お口の中の現状、親知らずの状態の詳細をご説明させていただきます。
親知らずを抜歯する方法や、親知らずを抜歯する前後の日取りや当日の流れなども詳しくご相談し、親知らず抜歯の日程を決めます。

3.親知らずの抜歯

親知らずの抜歯を行います。当日は、その後に予定を入れずにゆっくりと休めるよう、自宅で安静にしていただきます。痛み止め、抗生物質、うがい薬の処方を行います。

4.消毒

親知らずの抜歯した傷口の経過観察を兼ねて、消毒にお越しいただきます。
抜歯をした翌日と、1週間後に来院いただきます。縫合している場合には、1週間後の消毒の際に抜糸をします。

5.経過観察

傷口の経過観察を行い、傷口が良好になるまで経過観察を定期的に行います。
親知らずの手前の歯に虫歯がないか、歯周病が進行していないか、しっかりと歯ブラシが当てられるようになるか、というのも経過観察で拝見します。